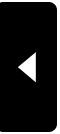2018年08月18日21:01

(伝統工法の斗組は、何度見ても飽きない綺麗さが有ります。)
虹梁や斗組や高欄を使用した屋台は、社寺建築の分野なので、それなりの経験が無いと
難しいものです。伝統工法をネットで調べると、意外と範囲が広く、難しい事が書いて有り、
何度も読み返して少しは分かりました。斗組の形や木割りも伝統工法の範囲ですが、
そこは、本体軸組が主でした。昔から、地震が多い国の日本では、色々と、工夫を重ね
何とか、地震に強い作り方にたどり着いたのが、この伝統工法だったようです。
昔から、一番簡単に家を、まっすぐに立てるには、斜めの筋交いが、楽に出来るはずですが、
古代建築では、筋交いの使用例は壁の中に数例だそうです。多分、地震で潰れた物が多く
出たからでしょうか?そこで考えたのが、柱に横穴を多く空け、貫板を通しクサビで固定して
建物を立つ方法でした。柱と虹梁や斗組も、当然、金物で固定せずに、木を組み合わせ、
少しの余裕を作り、地震の時は、木の柔軟性で建物全体を少しだけ、一時的に変形させ、
揺れを吸収して、受け流す構造のようです。建物を硬く固定しないで、柔構造に作る、
これが、地震の国、日本が考えた伝統工法だそうです。これ以上、屋台に合った作り方は
無いので、本当の伝統工法を考えて作らなければ行けないと思います。柔構造に作ると
言う事は、まず、無駄なボルトや金物を忘れる事です。
屋台と伝統工法と地震の国日本
カテゴリー
(伝統工法の斗組は、何度見ても飽きない綺麗さが有ります。)
虹梁や斗組や高欄を使用した屋台は、社寺建築の分野なので、それなりの経験が無いと
難しいものです。伝統工法をネットで調べると、意外と範囲が広く、難しい事が書いて有り、
何度も読み返して少しは分かりました。斗組の形や木割りも伝統工法の範囲ですが、
そこは、本体軸組が主でした。昔から、地震が多い国の日本では、色々と、工夫を重ね
何とか、地震に強い作り方にたどり着いたのが、この伝統工法だったようです。
昔から、一番簡単に家を、まっすぐに立てるには、斜めの筋交いが、楽に出来るはずですが、
古代建築では、筋交いの使用例は壁の中に数例だそうです。多分、地震で潰れた物が多く
出たからでしょうか?そこで考えたのが、柱に横穴を多く空け、貫板を通しクサビで固定して
建物を立つ方法でした。柱と虹梁や斗組も、当然、金物で固定せずに、木を組み合わせ、
少しの余裕を作り、地震の時は、木の柔軟性で建物全体を少しだけ、一時的に変形させ、
揺れを吸収して、受け流す構造のようです。建物を硬く固定しないで、柔構造に作る、
これが、地震の国、日本が考えた伝統工法だそうです。これ以上、屋台に合った作り方は
無いので、本当の伝統工法を考えて作らなければ行けないと思います。柔構造に作ると
言う事は、まず、無駄なボルトや金物を忘れる事です。