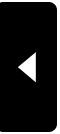2018年04月07日21:17

(欄干の柱を正確に作るには、角材のうちに加工するのが基本です。)

(鉾木の先に付いているのがヒネリアリです。地覆にタタラ束用の寄せアリも空けて有ります。)
最近、寄せられる屋台修理の相談で多く聞かれるのが、欄干の柱のぐらつきによる、
鉾木の外れと損傷などです。その原因を一口で言うと、伝統工法で作らないで
ネジとボルトで組まれていると言う事です。昔から伝わる屋台独特のその作り方は、
全国共通のもので、丈夫さを突き詰め、直ぐに、分解出来るように作られています。
これが、一人が考え広まったものか、複数が考え広まったかは、分らないようです。
普通、木組に良く使われるアリは、上下や左右の移動で利かすのが、常識ですが、
この屋台の欄干に使うアリは、ヒネリアリと言って、45度回転させる事によって利かす、
画期的な物で、その先に丸棒を付けて、柱の中で90度違う方向の木と、組み合わせる事は、
今の大工では、想像すらも、出来ないものだと思います。良く考えて見ると、
伝統工法は見えない所にアリを多く上手に使い強度を上げているのが分かります。
100年以上持たせるには、100年以上持っている屋台の、構造を真似る事が大事だと思います。
これから作られる屋台が、短命の原因のネジ、ボルトの使用を止め、優れた祖先が残してくれた、
伝統工法を使って屋台を作くられる事を希望します。なお、模型で色々ご説明出来ますので、
お気軽にお立ち寄り下さい。
伝統工法でしか作れない、丈夫な欄干や屋台本体。
カテゴリー │屋台作り
(欄干の柱を正確に作るには、角材のうちに加工するのが基本です。)
(鉾木の先に付いているのがヒネリアリです。地覆にタタラ束用の寄せアリも空けて有ります。)
最近、寄せられる屋台修理の相談で多く聞かれるのが、欄干の柱のぐらつきによる、
鉾木の外れと損傷などです。その原因を一口で言うと、伝統工法で作らないで
ネジとボルトで組まれていると言う事です。昔から伝わる屋台独特のその作り方は、
全国共通のもので、丈夫さを突き詰め、直ぐに、分解出来るように作られています。
これが、一人が考え広まったものか、複数が考え広まったかは、分らないようです。
普通、木組に良く使われるアリは、上下や左右の移動で利かすのが、常識ですが、
この屋台の欄干に使うアリは、ヒネリアリと言って、45度回転させる事によって利かす、
画期的な物で、その先に丸棒を付けて、柱の中で90度違う方向の木と、組み合わせる事は、
今の大工では、想像すらも、出来ないものだと思います。良く考えて見ると、
伝統工法は見えない所にアリを多く上手に使い強度を上げているのが分かります。
100年以上持たせるには、100年以上持っている屋台の、構造を真似る事が大事だと思います。
これから作られる屋台が、短命の原因のネジ、ボルトの使用を止め、優れた祖先が残してくれた、
伝統工法を使って屋台を作くられる事を希望します。なお、模型で色々ご説明出来ますので、
お気軽にお立ち寄り下さい。