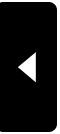2013年12月26日22:18

(斗組に、浜縁板を仮付けした状態 )
今年の1月、まず、300を超すマス作りから始まり、次に手間の掛かる、花肘木、拳鼻類
しのぎだけでなく、このような彫刻は大工の仕事なので、なかなか根気が必要です。
ヒノキに使う、彫刻刀ではケヤキの彫りは無理なので、小さなノミを改造しての使用です。
それから刻みに入り、ようやく組上がったのは、11月末でした。その部品数500余り
その、組上がった姿は、作った本人達も感心させるほどの美しさが有りました。しかし良く
考えて見ると、この斗組は、花肘木、拳鼻、木割などを江戸時代の形式のものを使っているので、
自分達が作ったのだが、自分達のもので無い、まさしく伝統美だと感じました。
そのため、誰が作っても同じようになってしまうので、残念ながら、屋台大工は裏方
のようで、半田の山車でも、製作した大工の名は載っていませんでした。
やはり、屋台の主役は彫刻のようです。
現在は、高欄の地覆のアリ組の仮固定をチェックしてからすべてばらし、
拭き漆仕上げに出し、ケヤキの手木の刻みに取り掛かっています。
屋台作り、その6、斗組は伝統美
カテゴリー │屋台作り
(斗組に、浜縁板を仮付けした状態 )
今年の1月、まず、300を超すマス作りから始まり、次に手間の掛かる、花肘木、拳鼻類
しのぎだけでなく、このような彫刻は大工の仕事なので、なかなか根気が必要です。
ヒノキに使う、彫刻刀ではケヤキの彫りは無理なので、小さなノミを改造しての使用です。
それから刻みに入り、ようやく組上がったのは、11月末でした。その部品数500余り
その、組上がった姿は、作った本人達も感心させるほどの美しさが有りました。しかし良く
考えて見ると、この斗組は、花肘木、拳鼻、木割などを江戸時代の形式のものを使っているので、
自分達が作ったのだが、自分達のもので無い、まさしく伝統美だと感じました。
そのため、誰が作っても同じようになってしまうので、残念ながら、屋台大工は裏方
のようで、半田の山車でも、製作した大工の名は載っていませんでした。
やはり、屋台の主役は彫刻のようです。
現在は、高欄の地覆のアリ組の仮固定をチェックしてからすべてばらし、
拭き漆仕上げに出し、ケヤキの手木の刻みに取り掛かっています。