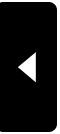2014年08月09日19:29


先日、見学に訪れた年配の方が、「この斗組は何段と言うんですか?」 と、
質問されました。何段?それには、何んとも答えられなかったのですが、本に
載っている一般的な事を説明して理解してもらいました。写真を見て簡単に
説明すると、桁の上に載っている、大きなマス(大斗)を基準にして、一つ
マスが前に出たもの一手先、二つマスが前にでたものを2手先と呼ぶもので、
この屋台では、二つ分、出ているので二手先になります。この近辺には、
二手先斗組の建物は、数少なくて、山梨の西楽寺がそれに当たります。
また、支輪と言う部材にも誤解が有り、この屋台では、マス上の通し肘木から
前の手先の通し肘木に掛かる斜めの板材の事を言います。この屋台は2枚有り
下の塗り物を板支輪、上の雲の彫った物を雲支輪と言います。また、その下の、鳥の
彫り物は、斗組の間に有るので、蛙股と言うようです。次回は彫り師の方から聞いた
事を書きたいと思います。
屋台作り その43 初めての屋台作りを終えて
カテゴリー │屋台作り
先日、見学に訪れた年配の方が、「この斗組は何段と言うんですか?」 と、
質問されました。何段?それには、何んとも答えられなかったのですが、本に
載っている一般的な事を説明して理解してもらいました。写真を見て簡単に
説明すると、桁の上に載っている、大きなマス(大斗)を基準にして、一つ
マスが前に出たもの一手先、二つマスが前にでたものを2手先と呼ぶもので、
この屋台では、二つ分、出ているので二手先になります。この近辺には、
二手先斗組の建物は、数少なくて、山梨の西楽寺がそれに当たります。
また、支輪と言う部材にも誤解が有り、この屋台では、マス上の通し肘木から
前の手先の通し肘木に掛かる斜めの板材の事を言います。この屋台は2枚有り
下の塗り物を板支輪、上の雲の彫った物を雲支輪と言います。また、その下の、鳥の
彫り物は、斗組の間に有るので、蛙股と言うようです。次回は彫り師の方から聞いた
事を書きたいと思います。